徳川家康公を御祭神
上野東照宮牡丹苑は、徳川家康公を御祭神とする上野東照宮の敷地内に、1980年4月、日中友好を記念し開苑されたものです。1/1〜2/下旬の冬牡丹と4/上〜5/上の春牡丹の年2回開苑されます。
今回は豪華な色彩を放つ冬牡丹の写真を掲載致します。
牡丹の花は豪華なので、中国では花王として愛されています。牡丹は中国の国花とされていた時代もあり、詩歌に詠まれたり、絵画に描かれ、愛でられて来ています。
「立てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は百合の花」 これは美人を形容する言葉ですが、実は漢方薬の世界で生薬の用い方の例えだったようで、昔は特に女性は静坐する機会が多く、下半身に血行障害が起こった場合牡丹の根の部分を飲用する事により血行が改善されるそうです。

写真術:花の上手な撮り方
Mr.Soutan:花を上手にとる3つのコツ
①構図:視点の工夫が上手の一歩
②光:自然光で撮影するのが最適
③カメラ:絞りを広く設定し、背景をぼかす
構図:視点の工夫が上手の一歩
豪華な色彩の冬牡丹
淡い黄色は光の色。白との差がないので難しい。
主役と真正面から勝負!
ボタンをさらに美しく!
中心部をバッチリ撮影
重なりや花びらのソフト感が表現できる。

ピントをやや手前に合わせる
花の揺らぎが伝わり、華やかな雰囲気を自然に表現できる。

花の中心や花びらの動きを意識する
幾重にも広がる八重の花びらの重なりの美しさが撮れる。

見上げる視点(3点透視図法)
設計図で使う3点透視図法。難しく考えない。
腰を下げる姿勢、あるいは寝転んで撮るという自分の体の位置を上下することで可能です。
花言葉「ひたむきな愛」が似合いそうな愛らしい一輪。

中心をちょっと右上に移動し、花びらの光と影を演出。

光:自然光で撮影するのが最適
花びらの光を表現する
午前中の光が最適。花びらが光を反射している雰囲気を撮りたいときは逆光もOK。
降り注ぐ日差しに透けるような軽やかな花びら。

「白鳥の湖」の4人の踊り子を思い出す
遠近感、動線、ムーブメントが表現できた一枚。

牡丹を寒さから守る「わらぼっち」
長い間、公家や武家屋敷で大切に育てられた高貴な花。

清楚な牡丹を守るのは当たり前
今は庶民の間に広まっている牡丹。でもわらぼっちで守るのは昔通り。

世界中の人々に愛される理由
その美しさは世界中の人々を魅了し、感動した人がさらに品種改良でパワーアップさせ、美の頂点を目指しているから。

花の形は一重、八重、千重、万重
松江の大根島の牡丹生産は日本一。始めは島の女性たちの行商で全国に普及。今では世界へ年間60万本を輸出する牡丹島。

カメラ:絞りを広く設定し、背景をぼかす
背景をぼかすことで、赤い牡丹をさらに王者の風格に仕上げます。花の写真の醍醐味。
赤色牡丹は王者の風格
主役を引き立たせるには周囲をぼかす。これは王道。
王者の牡丹を王道で撮影。(笑)

白い牡丹は高貴あるいは誠実
白い牡丹。背景をぼかすことで奥行きのある陰影を強調。

紫色の牡丹の花言葉
紫色のシコンノボタン(紫紺野牡丹)だけには「ひたむきな愛情」「謙虚な輝き」「平静」などの花言葉がある。
ブラジル産のこの紫色の牡丹は毎日休むことなく咲くためにこれらの花言葉が生まれたようです。

侍タイムスリッパーは江戸時代から現代へ
日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した侍タイムスリッパーより、はるかに時空を超えて広まった牡丹。その美しさはこれからも人々を幸せにする価値ある存在。
牡丹タイムスリッパー?
牡丹は中国の国花?
日本では、桜や菊が富士山と並んで日本の象徴になっているが、法律で定まった国花はない。同じく、中国でもまだ定まっていない。梅にしようか?蘭にしようか?それとも牡丹?
悩んではいるものの、国民の多くは牡丹が大好きで、ぜひ国花にしてほしいと願っているらしい。
ちなみにアメリカやイギリスはバラ、韓国はムクゲ、スペインはカーネーション。赤いカーネーションは母の愛を表現している。
牡丹は空海の土産?
以前、熊野古道から高野山に登った時に、一番驚いたのは観光客の多さだっだが、つぎにあちこちに咲き誇る牡丹の美しさだった。お札売り場の若い巫女さんにその美しさを称賛すると、
「300種類、600株以上あるんですよ」と即答してくれた。
「だってね」横から口を挟んだ年増の巫女さん、
「お大師様が唐からお持ち帰りになったんだもの」
まさかと思いながら、その場は去ったものの、その言葉がずっと心に残っていた。
空海は長安をイメージして高野山を築いた。だったら、長安の王宮の豪華なボタンを再現しても当たり前。
司馬遼太郎氏は空海を詩情・造形・色彩のある男と『空海の風景』の中で称している。
奈良時代か平安時代に渡来したといわれる牡丹。
天才的な空海が運んでくれたと想像するだけで楽しくなりませんか。信じるも信じないのもあなた次第。
でも、空海説はともかく、牡丹を愛し、育てる人々は世界中に幸せを分け与えているはずです。
黄色い牡丹はどこの国から?
フランス生まれの金閣とは?
フランスでは牡丹のことを「ピボワンヌ」(pivoine)という。
1919年にフランスで生まれた黄色い牡丹。日本で販売されるときは「金」を名前の頭につけることが多い。
例えば、金閣や金鵄(きんし)といった名前で、黄金のようなイメージを強調している。
米国生まれのハイヌーンとは?
アメリカでも近年改良が加えられ、それまで存在しなかった独自の黄色い牡丹を作り出し、成功を収めたのがハイヌーン。
ハイヌーンには正午とか、真昼間とかの意味があるが、確かに光が最高点になる色にも似ている。映画「真昼の決闘」もアメリカではそんな名前だったような記憶がある。
牡丹には色別の花言葉がない
牡丹の花言葉は、「富貴」「高貴」「壮麗」「王者の風格」「恥じらい」「誠実」「思いやり」などがある。他の花と違って、色別での花言葉はないそうです。
でも一つだけ例外が紫の牡丹。紫色のシコンノボタンには「ひたむきな愛情」(毎日咲く姿のイメージからの花言葉)
牡丹タイムスリッパー
2000年前、中国大陸の草原でひっそり美しく咲いていた牡丹の花。その後、時と空間をスリップ。日本やシルクロードを経て、ヨーロッパで見事に開花。さらにアメリカ人でさえ、その魅力に惹かれて、まさかの黄色い牡丹まで改良し、世界に発表した。
今なお、時空を超えて開花する牡丹タイムスリッパーは人々を永遠に魅了している。
「空海の風景」で司馬遼太郎が「空海が苦難の旅を経てたどり着いた寺院の庭に咲き誇っていたのは牡丹の花々」と書いていた。
その文章を読んだ時に、もし空海なら、牡丹の美しさはもちろんだが、その薬効に気がつかないはずはない。必ず根っこを持ち帰って、お寺の庭に植えたはずと思った。
空海は身体にいいものを見つけ、仏教の布教の助けにしたはず。各地に残る温泉発掘のポイントは空海の伝説が数多く残っている。牡丹もそのひとつではなかっただろうか?
タイムスリッパー。牡丹も時と空間を超えて世界中へと羽ばたいたが、空海の教えも今なお人々の心をしっかりつかんで離さない。高野山を訪問した時、戦国武将として戦った人々の墓が隣同士に並んでいた。あの世では仲良く暮らしているに違いない。
高野山には思想や権威を通り越した先の未来の世界があると感じた。もしかすると空海こそがタイムスリッパーだったのかも。
写真は楽しみを生み出す
写真術は撮影スキルだけでなく、様々な想いを広げることで楽しみが生まれる。ゆとりを持って、シャッターを押すときも慌てないことが大切。
美しい牡丹を育てるのは至難の技。でも苗からならできるかも。そんなあなたにお勧めです。
苗木:赤い牡丹「太陽」
苗木:黄色い牡丹「黄冠」
書籍:造園実務必携/藤井英二郎
毎月1日と15日に更新予定。お楽しみニャン!
Copyright © 2025 painted by Mr. Soutan. All Rights Reserved.

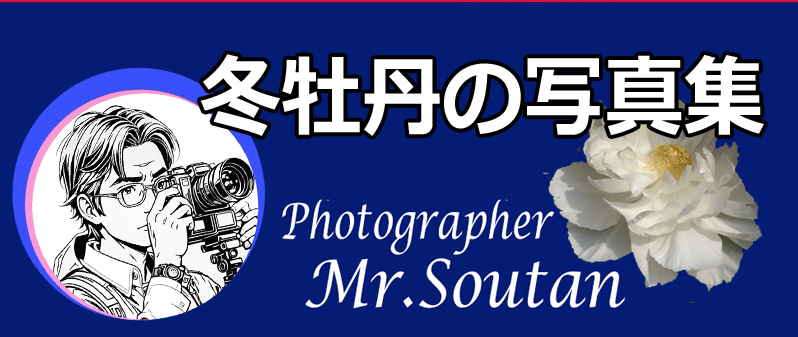
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/461a9ff7.be88bfba.461a9ff8.cef0ffd0/?me_id=1221694&item_id=10000871&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhana-online%2Fcabinet%2Fbotan_hana%2Ftaiyo1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/461aa69e.f1e036e4.461aa69f.39a6a47c/?me_id=1224087&item_id=10000083&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fuchidenouen%2Fcabinet%2Fi%2F09509563%2F04491604%2Fimgrc0066498133.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/461aa3ec.cc334335.461aa3ed.69d938c6/?me_id=1276609&item_id=12275702&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F00944%2Fbk4254410387.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)